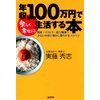太陽光発電が社会の隅っこで光を発し始めてから何年が経過するのでしょう、人工衛星の発電パネルなどの目的で搭載が始まってからならばおそらく何十年?でしょうか。
建築主さんの相談事の中には「太陽光発電パネルは取付けはどうしましょう?」というのが何度と無く繰り返されてきましたが、ご本人の強いご希望が無い限り積極的にはお奨めしてきませんでした。
地球温暖化防止あるいは環境配慮のためとはいえ流行の投資としては大きすぎて、設計を生業としているものとしては商業的な魅力を感じませんでし、安直に流れにも乗ること自体あまり好きではないからです。
何十年もそんな時が過ぎてきて、今年3月の東日本大震災や原発の事故、身近にも頻発する地震、これらを見ていて沸いてきた思いがありました。
生活に必要な「衣食住」、それらは自給自足できたらいいだろうな・・・・・
うちの母親は毎日畑で野菜作りしています、「食」の自給自足です。
「衣」の自給自足は大変そうだから素直にに妥協しても(笑)、エネルギーの自給自足も出来るようになればいいなあ・・・・・とすごく素直で単純な発想です。
メンテナンスが複雑で自分で出来ない機械に頼るばかりでなく、エネルギーも自己完結できる家がいい、究極は電線に繋がれていない家がいい、でもネットに繋がれてないと「ブログオタク」としては辛い(笑)
売電額が定期預金の金利より有利なのは面白い魅力ですが、近い将来、電気自動車や蓄電池が家庭で安価に手に入るときが来れば昼間発電した電気を夜間使用したり、自動車を充電したり出来たら・・・・
あるハウスメーカーは既に実現していることも知っていますが、さらに発電効率の良い革命的なパネル開発が進んでいるニュースを聞くにつけて日本の大多数の家庭がそうなる気がします。
アシモの指が器用に動くようになった時代がやってきて、「鉄腕アトム」が現実に生まれそうな今日この頃、自分はアトムに介護してもらうかもしれない。
未来を夢見たい、そんな思いも手伝っています。