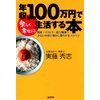「まちかどけんちくか」とひらがなでグーグル検索してみると、おそらく国営放送局のまちかど情報室やまちかど建築展などがあがってくることでしょう。
まちかどの後のけんちくかを打ち込むとトップ表示してくれます、当然ですよね唯一ですから・・・・きっと孤独な存在なんでしょう?
まちかどけんちくかは「建築家」ではなく「すぎはら設計」や「杉原寛」の装飾ことばを指しているのではないんです。
「けんちくか」は賞をたくさん取って有名な「建築家」ではありません、カリスマ性もなく一流大学も出ていません、けれども建築が好きで一生懸命勉強しています。
いつ努力が実るか分からない、実るとも思っていない無欲さが肩に力が入っていなくてお付き合いが楽な存在でありたい。
発想の奇抜さや時代を写し取ったようなデザインでマスコミの注目を浴びることで存在感をアピールして自分の社会的価値を揺ぎ無いものにしたいというベクトルは向かっているのだが、それを最終目標にはしていない。
政治的人脈などもろもろの人脈が武器とも思えない。
ここまで書くとまるで世捨て人みたいですね(笑)
考え方のベースにあるのは「生活の容器」とか「人生の場」といったこと。
デザインからは非日常性を感じるように、逆に日常性や生活観から個々の人生を充実させてくれる「住まい」。
ひとりひとりの建築主と向き合ってその人の「住まい」の具現化してくれる「けんちくか」はどこの「まちかど」にも存在できるはず。
これらの思いを凝縮した言葉だったのです。