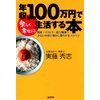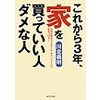今日もこの時間、午前3時前には目が覚める。
お教えできない事情があります。・・・・なんて書くと次を読みたくなるでしょう?
こんな血流の見えるようなブログを書いていると簡単に本音を公開しちゃっていいのかと心配になると思われませんか?
一日に200人から300人がひょっとしたら覗いてみえる、私の気持ちを。
でもその半数以上は通過するだけの人たちだと思いますが・・・
ブログなんてむちゃくちゃ多くの人に見られていると思いきや、意外と面識のある方々しか見ていられないようにも思う。
なぜかといえば、それ以外の方々は私の思いに興味がある訳がない・・こんなおじさんの呟きに何てことないはずです・・・(笑)
この・笑・記号自体おかしいでしょ、おじさんくさくて。
毎日、毎日、設計図のことばかり考えている人間は機械のように思えるかもしれませんが、こんな匂うような話題が書きたくてウズウズしています。
脈略のない内容ですが最後に一言、私のような設計屋に仕事を託すと本当、お得ですよ。
自分に素直で嘘をつけないオヒトヨシ、欲がない分時間かけてじっくり作ってしまいます。
詳しくはではまたおいおい説明します。というか読んでると分かってきます。